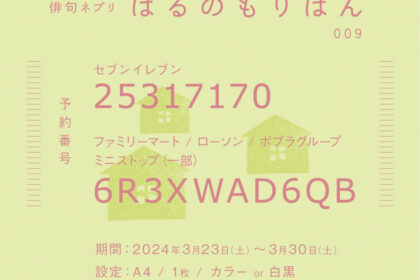エッセイ|ゆめみがち

夏になると思いだすのは、雨の降りはじめ、むうっと立ちのぼるアスファルトの匂い。
わたしはそれを地面に伏しながら、嗅いでいた。これはわたしが小学一、二年生ごろの、実際にあった話である。いや、話というには大げさな気もするような、ただのひと場面。
明日から夏休みだった。終業式をおえ、帰路についていた。さんすうセット、鍵盤ハーモニカ、クラスのなかでただひとり、わたしだけ花が咲かなかった、朝顔の鉢植え等々。なぜ前もって、すこしずつ持ち帰らなかったのか。じわじわと後悔にさいなまれていた。親からも教師からも、持ち帰れとか、言われた記憶がまるでない。それらすべてを身体にたずさえ、わたしはちんどん屋さながら、ふらふらと歩いていた。
家族四人で住んでいた一階がテナント、二階が住居だったアパートまで、あと半分というところだった。わたしは何かにつまづいて、転んだ。すべてが地面に散らばった。さんすうセットからは、花のかたちをしたおはじきが飛んでいった。赤とか青色をした、おはじきのほんとうに小さな、花びら一枚のぶぶんに、母親の字でわたしの名前が書かれていた。
小雨が降っていた。わたしは起きあがれなかった。なぜなら、あまりにうっとりとしていたからだ。
頭のなかで「わたしはなんて、かわいそうな女の子なのだろう!」と思っていた。この悲劇的な状況。姉の持っている少女漫画のなかや、アパートの一階で、自営業をしていた父の仕事場に置いてあるテレビで、いつも見ていたドラマやアニメのなかにこんな状況、出てこなかっただろうか。わたしはその、主人公なのだ!
「ちょっと! あんた、何しとんの?」
声をかけられ、はっとした。どれくらいそのままで居たのだろうか。声の主は、父の仕事場の二軒隣で喫茶店を営むおばさんだった。身体が大きくてパンチパーマで、おばさんはいつも、足首くらいまである長さの黒いワンピースを着ていた。
にもつが多くてね、ころんでまってね、ともごもご説明しながらわたしはさっと立ちあがり、おばさんの運転する車に乗って、アパートまで一緒に帰った。おばさんはずっと怪訝そうにわたしを見ていて、しだいに夢から覚めていくような気持ちになった。
ゆめみがちな子どもだった。ほんとうは小学校に入っても、授業中にずっと座っている意味が、よくわかっていなかった。それからいくどとなく、なんどもなんども夢から覚めるようなできごとに遭遇しながら、いまなお、わたしはゆめみがちである。
初出 : zine『garden 庭 vol.2』(2019)より、加筆・修正しました