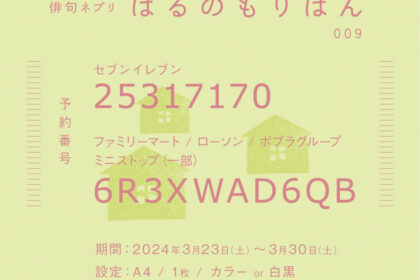二〇二一年三月十八日(木)

乗代雄介『旅する練習』(講談社)を読みおえ、しばし茫然とする。
どれだけ夫に環境を整えられても、けっきょくストーブのまえに座りこみ本を読むことをやめられない(すぐ腰がやばくなる)。このときも、わたしは床でストーブの熱に焼かれていた。頭上にある椅子に座った子どもの背中をちらちらと見あげては、叫びだしたい気持ちを抑えながら、ゆっくり息を吐きだしていた。
一昨日から風邪の症状があり、まだ微熱があった昨日から本書を読みはじめた。体調がわるいとよけいに、文字を目で追いかけたくなって、やっと読みたかった本を手にとったのだった。このところ句集ばかり読んでいたから、久しぶりの小説だ。今日は園が午前保育だったため、昼から子どもが居たけれど、夕飯を簡単なものにしたので、本を読むチャンスが思いのほかあった。
物語は昨年の三月あたま、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学校が臨時休校になった頃から始まる。サッカーがとてもすきで上手く、強豪校への中学受験に成功した亜美と、近所に住む小説家の叔父で語り手の〈私〉は当初、鹿島アントラーズのホームゲームを観にいくついでに、以前亜美が鹿島にある合宿所の本棚から、持ち帰ってしまった本を返しにいくという計画を立てていたが、やむなく中止になる。そこでふたりは〈私〉の提案により、千葉の手賀沼から鹿島のある茨城まで、利根川沿いを歩いて目指すことを決める。
面白いのはただ歩くのではなく、亜美は堤防沿いをドリブルしながら進み(すごい!)、ときおり〈私〉は立ち止まり、目にした鳥や花などの風景をノートに描写する(そのあいだ、亜美はリフティングしている)ことだ。ふたりにとって、それはお互いにふだん行っていることの練習であり、亜美はこの旅を「練習の旅」だという。風景を描写することについて、それ自体が小説なのだと、保坂和志さんが言っていたような、ということがふと思いだされる。〈私〉と似たことを酉島伝法さんがしていた気がすると、読みながら思っていたけれど、作者の乗代さん自身がしていることだと後から気づく(また、このことについては後述します)。
ふたりの旅には途中から、大学四年生のみどりさんが加わる。本書は亜美がとても明るく、読んでいるとこちらまで元気になってくるのだが、自分に自信がないというみどりさんのこともわたしはすきだ。彼女はある細やかな理由から、ジーコのファンなのだが、そういうことってありそうだ、と思わされる。推しと出会うということは、そんな些細な瞬間なのかもしれない。関東圏の地理やサッカー、たびたび話題にのぼるアニメ「おジャ魔女どれみ」。どれにもわたし自身はあかるくないのだが、それでも本書を面白く読むことができた。〈私〉がこの旅のさいごに行う風景描写の練習、とりわけ美しい場面に、わたしはずっと心を掴まれたままだ。
作者と作品は基本、べつものであると思っている。作者のもつ背景を、作品に影響させずに読みたい。それでも自分は作者を知りたいという、ミーハーともいえる気持ちをもっているほうだと思う。前作『最高の任務』(講談社)を読んだあと、たまたま目にして読んだインタビュー「作者の読書道」がとても面白く、乗代さんに興味をいだいたのだった。
とくに印象的だったのが、読書の際に大量の引用をノートに書いていること(すぐに真似したが、続かなかった)。『最高の任務』にほのかに感じた山本直樹味についても、答え合わせのような返答があった。先述した風景描写についても、このインタビュー内に載っている。そういった作者への興味から、新刊がでたら読まなきゃという気持ちもあったのだが、今後も乗代さんの作品を読みつづけたいと、本書を読んで思いなおした。
ここを通り過ぎて銚子まで歩いたこともある柳田國男は、これとよく似た感動を紹介している。蘭領の島で稲作をしていた友人が何日も寝ずに働いた後に小屋で休んでいた時、「團場の上を白鷺のような鳥が二三羽、緩やかに飛びまわっている」のを見て、「何ということなしに、居合わせた者が皆涙をこぼした」というのだ。「つまり人間の努力の前に、自然がなよなよと凭りかかる光景が快いのである」
柳田が断じている感動は、努力して土地を手懐けた百姓のもので、訪れては帰るだけの気楽な旅人ならまだしも、よそ者が感じやすいものではない。小島信夫の不敵な気楽さはその感動を容易に引き起こすが、同時にそれへ甘んじることを戒めるような忍耐に関する不思議さも書き込まれている。
そして、本当に永らく自分を救い続けるのは、このような、迂闊な感動を内から律するような忍耐だと私は知りつつある。この忍耐は何だろう。その不思議を私はもっと知りたいし、その果てに心のふるえない人間が待望されているとしても、そうなることを今は望む。この旅の記憶に浮わついて手を止めようとする心の震えを静め、忍耐し、書かなければならない。後には文字が成果ではなく、灰のように残るだろう。
『旅する練習』P103-104