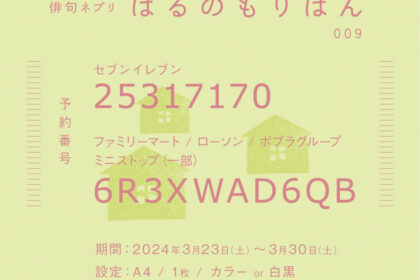掌篇小説 | ドライブ
当然、というふうだった。巻(まき)の運転する深緑色の軽自動車が、駐車場へ向けカーブを切る。
広い道路沿いにブックオフがあった。そこが彼の、ふだんから利用している店舗だったのかは、聞きそびれたので分からない。
それだけじゃない。わたしはいろんなことを聞きそびれた。一年間、浪人していた理由とか。彼は大学の後輩だが同い年だった。聞く時間はその日、じゅうぶんあったはずなのに。
巻との二回めのデートは、いちおうの目的地を彼の自宅としていた。それぞれべつの県に住んでいて、その間は車で二時間以上かかるため、だいたい真ん中あたりだという駅に呼びだされたのだった。そこから彼の住む地域まで、思っていたよりながいドライブをすることになり、終電を逃した帰りには、わたしの自宅まで、さらにながいながいドライブをすることになる。巻が道に迷ったからだ。
はじめてのデートで行った居酒屋で、お互い本が好きであることを知った。彼がいちばん好きだという村上春樹を、その頃はまだ読んだことがなかった。そういえば、日本の小説について学べる科もあったのに(わたしはそこに属していた)、外国に関する文化を中心に学ぶ科に彼がいたことも、当時はふしぎに思っていた。
大型のチェーン店が立ち並ぶ、均質化された地方という点で、助手席から見える風景は、自分の住んでいる地域とさほど変わりがない。お金もなく、本が好きだから、ブックオフへ行く。それが自分にとっても日常だった。なんならそこには、地元の新刊書店より本が置いてある。
まず巻は百円文庫本の棚へ、ずんずん進んでいった。「日本人作家 あ行」と書かれた札のまえに立ち、そこから順にひとつずつ、睨みつけるようにじいっとタイトルを見ていって、たぶん芥川とか乱歩とか川端とか、目ぼしいと思わしきものをひょいひょい手に取っていく。自分の好きな作家の本がありそうなコーナーだけを確認し、目当てのものが見つからず、はやばやと暇になっていたわたしは、そんな彼の姿を黙ってじいっと見ていた。
ものすごく新鮮だった。そうか、そうすればいいのか。この方法なら、自分の探している本だけでなく、無意識に気になっていた本にも出会えるかもしれない。ただただ、そう感心していた。
彼は自分の部屋に入ると、戦利品である文庫本のカバーをつぎつぎと剥がしてはゴミ箱へ捨て、本棚に並べはじめる。彼の本棚には、同じように手にいれたのだろう、色褪せたうすいベージュの文庫本が、ぎっしりと詰まっていた。統一感があって綺麗だ。わたしは彼から差しだされた酒を飲みながら、ぼんやりとその背表紙に書かれたタイトルを眺めていた。
それが巻とのさいごのデートになった。わたしが大学を卒業するまでの一年ほど、彼から無視されつづけたからだ。
ショックだったいっぽう、しかたないか、という気持ちもあった。ドライブは居心地がわるく、わたしはずっとうわの空だった。
帰り道、車内で好きだと伝えたとき、巻の眉間にはぎゅっとしわが寄っていた。一回めと二回めのデートの間に、わたしは彼に嫌われてもおかしくない、あることを、しでかしていた。だから、デートに誘われたことじたいが意外で、これ以上嫌われないようにすることばかり、助手席で考えていた。
どうして無視するのか。嫌われたことは、すでにあきらかであるし、自分が傷つくことを恐れたわたしは、さいごまでそれを、巻に聞くことができなかった。だってどうにもならない。でも、聞いていたのなら、こうやって十何年も経ったいま、彼を思いだすことはなかったかもしれない。
わたしはブックオフに行くと、まず百円文庫本の棚へ向かうようになった。「日本人作家 あ行」のまえで仁王立ちになり、いちど大きく、息を吐く。そして順にひとつずつ、タイトルを目で追いかけていく。ながいながい時間が流れる。目はかすれ、頭は酸欠になったかのように、びりびりと痺れている。好きなひとに無視されようと、わたしが消えるわけでもなかった。目のまえには、まだこんなにも、読んだことのない本がたくさんある。
そのなかで、彼の本棚にあったものを、見つけることもあった。なんだそれ、と自分につっこみながら買った、遠藤周作『わたしが・棄てた・女』、三島由紀夫『女神』、村上春樹の著作いろいろ、たしかさいしょに読んだのは『蛍・納屋を焼く・その他の短編』……。それぐらいしか憶えていないけれど、むさぼるように読んでいた。カバーを剥がすことも真似していたが、面倒になってすぐやめた。村上春樹のことはとくに好きにはならなかった。それらの本はすでに処分したものがおおいが、まだ本棚に並んでいるものもある。
そうやって、わたしは彼のことを知ろうとした。けっきょく何ひとつ分からないままだった。
(了)

本作は出版社である夏葉社さんの、インディペンデントレーベルである岬書店から発行された『ブックオフ大学ぶらぶら学部』が、めちゃくちゃ面白かったいっぽうで、いろんな思い出や感情が溢れだし、なにか書かずにはいられない気持ちになったものを、掌篇小説というかたちで勝手に書いたものです。
地方に生まれ育った身としては、まさに〈自分はブックオフと共に成長してきた。そして、成長し続けている〉(同い年である、武田砂鉄さんのエッセイ『ブックオフのおかげ』より引用)という、実感がある。わたしはブックオフが大好きだった。もっとも通っていたのは十代半ばから、二十代半ばくらいにかけてだっただろうか。その頃も、いまも、本好きであると言いながら、ブックオフが好きだと言うことには、どこか後ろめたさがつきまとっていた。どうして、いつもあんなに探しているものが、欲しいものが、そこにはあったのか(実際には、本書にも出てくるように、はずれの日だってある。それでも手ぶらで帰りたくなかった)。
ちなみに本書は、最終ページの執筆者プロフィールも面白い。先述の砂鉄さんの場合は〈ブックオフ大学値札チェック学部値下げ待機学科〉、発行人の島田潤一郎さんの場合は〈ブックオフ大学ぶらぶら学部岩波文庫学科〉とある。もし、あの頃の自分に入学が叶うのだったら、ブックオフ大学ぶらぶら学部近代文学ぜんぶ読みたい科センチメンタル専攻、かなあと夢想する。
もう当時のような情熱も、体力もないけれど、ブックオフには行く。これが現時点での、わたしの成長としたい。
島田さん、面白い本をつくってくださり、どうもありがとうございました。