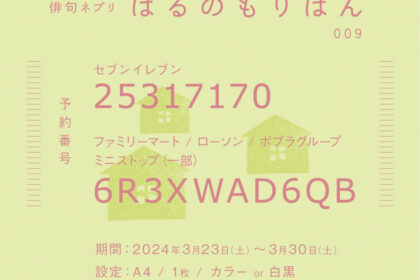楠本奇蹄句集『おしやべり』を読みました。

楠本奇蹄さんの『おしやべり』は、第11回百年俳句賞最優秀賞を受賞した同タイトルの連作50句をまとめたミニ句集。賞の主催社が発行する雑誌「100年俳句計画」2022年1月号の付録として付いてくるものを手にいれました(現在、残念ですが品切れになっているようです…)。
奇蹄さんは句集で作品が読みたいと個人的に思っている俳句作家さんのひとりで、本というかたちで読めたことがうれしいです。また、第12回北斗賞の准賞を受賞されたことも記憶にあたらしく、また句集を手にできるのもそう遠いことではないかも…?と思っています。本当におめでとうございます!!!
本作は連作であり、隣りあう句のつながりも素晴らしいので、そこから取りだすのもどうなのとか、そもそも全部すきなので…という気持ちもありますが、特にすきな5句と稚拙ですが感想です。
聖五月ひつじにひかりひとつずつ
光あふれる初夏、しろい羊の群れがある。季語から神の子羊イエス・キリストや、「いけにえ」というイメージも導きだされ、光があるから生まれる翳りにも惹かれる一句。ひつじが自分も含め人間たちに思えてくる
脱いだ服ほどのはつねつ夏座敷
虹がはじまる家々をぬけがらにして
隣りあっている二句。「脱いだ服ほど」という比喩にまず惹かれ、開かれた「はつねつ」の軽やかさに夏座敷の重みという対比にどきりとする。脱いだ服とぬけがらの、つながりがあるようなイメージもすきで、古めかしい家々から飛びだしていったような物語性も感じる
小春日は梯子の翳の逃げたい日
冬の季語のなかではあかるい印象で、個人的に使いがちな季語「小春日」。でも、この後ろめたいような気持ち、なんだか「わかる」となる
白鳥は来ぬ虹彩の草臥れに
奇蹄さんの句には、季語(掲句だと白鳥という動物)と身体の境目がないような印象をいだくことが多いが、こちらもそう思った。「草臥れ」(くたびれ)という表記には、疲れたという意味以外にも、視覚的に訴えてくるものがある。目ではなく、虹彩という部分を取りだしている点もすき