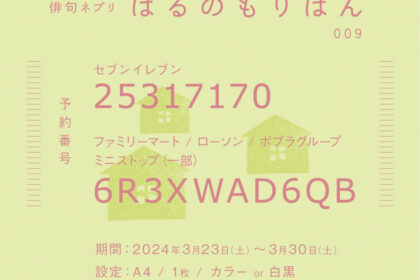日記 | 三月十一日(水)

九年前なにをしていたか、朝食を食べながら夫と話す。もう閉店した地元のヴィレッジヴァンガードに、ふたりでいたこと。それぞれ別の場所で、わたしたちは揺れる商品を見て、首をかしげていた。それからは、いつ死んでもいいように生きよ、という姿勢だったが、気がつけばいまは、いつなにが起こっても、まず生きのびようと思っている。
朝風呂(半身浴)する。自分にとってかなり贅沢で、いつも多幸感にあふれる行為なのだけれど、今日はそれが訪れない。湯をためたあとにすぐ入らずほかごとをしていて、湯がすこし冷めてしまったせいだろうか。さむい。身体があたたまるまで、湯舟でじっとしていたら、午前中がほとんど終わっていた。
スーパーで買った袋の酸辣湯麺を昼食に食べ、書きたかったメールの返信を二件、やっと送る。ひとつは友だちへ、謝らないといけないこと。もうひとつはF社への、お礼のメール。
いつなにが起こるかわからない。だから、いつか書くだろうと思っていた小説を書かなければと、書きはじめたのが九年前。その年のおわり、F社主催の賞に応募した掌篇が、受賞したという報せが届いたのだった(その手紙を受けとったときの、ふるえるような喜びは、いまでもありありと思いだすことができる)。
受賞作の著作権は主催社側にある。もちろん納得していて、約九年間を過ごしてきた。だが、本をつくりはじめて生まれたのは、この作品を自分で手わたすことができたらいいのに、という気持ちだった。これまでにあった、「自分の思いえがいた完璧な作品をつくりたい / そんなのできない」という葛藤が、日記本をつくったことで、ぺりぺり剥がれた。わたしは自分で思っていた以上に、この作品をあいしているのかもしれない。
頭のなかで「でも」「どうせ」を繰り返すのがいやになった。とんでもなく失礼なことを聞いているんじゃないか?というのは承知で、次作zineに受賞作を掲載することは可能か、メールでお尋ねしたのだ。そして、しかるべき手続きをおこなうことで、それが可能になるという返信を、応援の言葉とともにいただいた。お世話になった担当者さんへ、お礼の言葉をつづっていたら、涙がぶわあとあふれて、とまらなくなった。
夕飯はさばの塩焼き、ブロッコリー蒸し焼き、なめこと豆腐とわかめの味噌汁。マカロニサラダ、おひたし(昨日の残り)。
牟田都子『校正者の日記 二〇一九年』(栞社)を読了。もともとあった、校正者さんへの尊敬の念がより、つよくなる。寝る前に、非常持ち出し袋に入れている、飲料水の賞味期限がまだ切れていないことを確認。