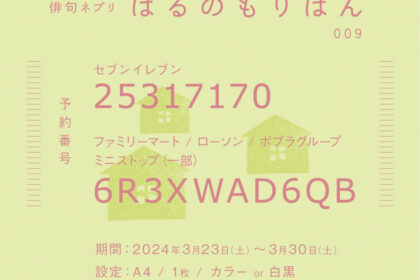午前三時の日記、あるいは対話 / その後の、親愛なるヒロインズ
午前三時の日記、あるいは対話

書きなさい。とにかく、何がなんでも書きなさい。
彼女の声が聞こえる。身体に流れこんでくる。
うまく生きられず自分がめちゃくちゃになってしまったら、それについて書いて。
「何からはじめる?」わたしはわたしに聞いてみる。
「何からはじめたらいい?」というかぼそい声がする。何かをはじめることに、いったいだれの許可がいるのだろうか。
あなたがこれまでにしてきた経験が、文学の題材としてふさわしくないなんてくだらない言葉を、絶対に、絶対に信じてはだめ -P321〜322
わたしの午前三時。それは、耳をつんざく、娘の泣き声で目覚める時間。
だいたいいつも、おなじ時間であることに感心する。娘は二歳を過ぎて数ヶ月。むなしくなるから「夜泣き いつまで」と、ネット検索するのはやめた。この時間に起きると妙に目がさえてしまう。以前は布団のなかで、自分のブログに投稿する文章をiPhoneに打ちこんでいた。内容は日記だが、その日のうちにほとんど書きおわらない。〈ヴァージニア・ウルフが書くことを許されたのは一日たった一時間だった。ゼルダは二時間〉-P279、家事と育児に追われるわたしは三十分から一時間くらい。
午前三時。いまは、この文章のことを、かんがえている時間。こまぎれになら時間はあると気づく。その断片をつなぎあわせて書いている。もちろん、SNSなどネットを眺めているだけで、過ぎていく時間も多い。iPhoneの画面を夢中で見ていると、娘はわたしに「起きて」という。
〈私がいちばん書きたいもの? 小説が書きたい。だってそうでしょ、何かを書く人は誰でもそう思ってるはず〉 -P28
どちらかというと日本文学にしたしんできて、海外文学にあかるくない自分が、リトルプレスやzineを探していて辿りついた「SUNNY BOY BOOKS」のサイトで、ケイト・ザンブレノの『ヒロインズ』が出版されると知ったとき、どうしようもなく惹かれたのは、わたし自身がずっと、作家になりたい無名の人間だったからだ。
物心ついたころから小説が書きたかった。小二のとき猫が主人公の物語をはじめて書いた。つぎにやっと書けたのが二十九歳で、これも猫がでてくる掌篇。ある通販会社主催の小さな文学賞で、賞をもらった。そのあと何作か書いたけれど評価はなく、子どもが生まれてからは、小説が書きたいのかもわからなくなってしまった。仕事は地元の岐阜で、無記名の記事ばかり書くライターをしている。
自分を見失っていた。育児は未知すぎて、四ヶ月めに帯状疱疹が顔にできた。二〇一八年六月、何を書いてもいいのだと、日記の形式にすがるようにブログをはじめた。タイトルは「Brunfelsia おもな登場人物はわたし」。Brunfelsia(ブルンフェルシア)はナス科の植物バンマツリの英名だ。スーパーの一角にあった小さな花屋で、その一種である「カオリバンマツリ」を見たとき、思わず吹きだした。わたしの名前はばんかおり。
〈私が書いているのは、陰の歴史についての本。書かれた本の陰に隠れた歴史〉-P25
七月に通販がはじまるやいなや、すぐ手にとった本書だが、第一章を読みすすめるのに時間がかかった。アメリカのモダニズム作家たちの周縁で、見えない存在にされてきた〈狂気の妻〉たちのことを、わたしはほとんど知らなかった。いまでは親愛なるヴィヴィアンとゼルダ。彼女たちのことをザンブレノの文章をとおして知ったとき、あまりに知らなさすぎたと愕然とするのと同時に、すでに知っていることなのに、知らないふりをしていたような気持ちになった。自分も抑えられていることに気づき、その正体を〈陰の歴史〉とともにあきらかにしていく。重苦しくても、必要な読書体験だった。女性というだけで抑圧されている。それは、現代のわたしたちまで地続きで(二〇一八年はとくに怒りの年)、見て見ぬふりすることは、もうできない。
第二章で、自身の創作講座の生徒である若い女性に、ザンブレノが声をかける場面がある(P321)。本当に書きたいことを書ききれていなかった彼女へ、〈書きなさい〉ときっぱりいうザンブレノの言葉に胸が熱くなり、いっきに目のまえがあかるくなった。わずかなわたしの小説も、自身の体験をもとにしている。いつかそこから離れた作品を書かなければいけない。書けないから自分はだめだと、ずっと思いこんでいた。〈フィクションこそが高くそびえる唯一の到達点で、つまりは神だったから〉-P369 わたしは〈書きたくて、書けなくて、それでも書かずにはいられない女性〉-P121 なのだ。到達点はひとつではないと、やっと気づけたばかりの。
ザンブレノがブログにコメント欄をつけたという一文を読み、自分のブログにもつけてみた。迷いもあったが「つけたいと思ったってことは、やってみろってことじゃないの」と、デザイナーの夫が設けてくれた。ブログをはじめた当初、夫に読まれたくない気持ちもすくなからずあった。要は夫を筆頭に、他者の目を気にしていたのだが、いまその気持ちはほとんどない。ひとに見られることを前提に、公の場で日記を書く行為には、〈自己検閲という暴力〉-P336 をこえていく力があるのかもしれない(自己検閲ゼロとはまだ言いきれないけれど)。夫はわたしのやりたいことをサポートしてくれている。
〈そのとき自分に起きていることすべてを書いておきたかった-自分自身を理解するために〉-P367まさしくそうだ。そして毎日書きたかった。わたしは自分をとり戻そうと、必死だったのだ。書いているうちに、水中にふかく沈んでいた気持ちが浮きあがってくる。日記を書くことは、まるで自分と対話をしているようだ。そして、誰かとも対話したいと思うようになった。コメント欄にはコメントをもらえた。友人のあまりいないわたしだが、趣味をとおしTwitterなどSNSでの繋がりができ(創作関連よりも、リトルプレス『マーマーマガジン』の編集長・服部みれいさんが発信している、音声メディアファンの仲間がおおい)、ブログの感想をもらうことがある。それが救いや励みにもなり、ネットがなければもてなかった繋がりに、感謝している。
さあ、あなたもやってみて。-P400
ザンブレノの声をうけ、わたしはまず、この文章を書いた。
本書を十一月に読了したあとは、読みたい本が膨大にふえ、ほとんどがまだ読みかけだ。いつか読まねばと思っていたウルフの『自分ひとりの部屋』、「ワルツはわたしと」が収められた『ゼルダ・フィッツジェラルド全作品』、ザンブレノの熱い語り口に惹かれ、ぜったい読みたいと思ったジーン・リースは、日本初の短篇集『あいつらにはジャズって呼ばせておけ』(タイトル最高)が電子版で発売され、キャシー・アッカー『血みどろ臓物ハイスクール』も文庫で復刊されたばかりである。
フェミニズムに関しても本を読み、学ぶ必要がまだまだあるし、わたしにとって「日本のヒロインズ」はだれなのかも、かんがえ中。崇拝にちかい気持ちをいだいている、自分のすきな作家たちが、じつはそうかもしれないと思いをはせる。
『第七官界彷徨』の世界に魅了されている尾崎翠。彼女は頭痛の薬による幻覚症状にみまわれ、東京から郷里の鳥取へ、兄に連れ戻された。日記といえば、つねにわたしの念頭にある『富士日記』の武田百合子。現在ではおそらく夫の泰淳よりも有名な彼女に、あまり抑圧という印象はなかった。パワフルで、家事に夫のサポートにと、とにかく何でもやっていた彼女。そのすべてを時代のせいにしていいものだろうか。でも、ヴィヴやゼルダに関し、「写真」や「スケッチ」という言葉が侮蔑的に使われたのにたいし、「絵葉書の写真をバカにしてはいかんぞ。泥臭くて野暮臭くて平凡さ。しかし隅々まではっきりていねいにうつしてある。それだけだって大したもんだ」-「絵葉書のように」-P42 武田百合子『あの頃』所収(中央公論新社)と妻にいう泰淳の言葉に、しみじみもする。
「日本のヒロインズ」については、文筆家の山崎まどかさん、ウルフの翻訳を手がけられた片山亜紀さんが、Twitterで幾人か名を挙げているのを拝見した。そのなかで、おふたりとも挙げていたのが矢川澄子だ。わたしは彼女と同じ誕生日。ただそれだけで、ずっと気になる存在だった。でも年譜的な情報を知るのみで、それ以上知ることがどこか怖かった。わたしたちは自己犠牲なんて似合わない、獅子座の女(ちなみにゼルダも獅子座だ)。いまあらためて、彼女のことが知りたいと思っている。
いろんなことが途中だ。これが現時点のわたし。
誰がなんと言おうと私たちこそ、私たちの物語のヒロインなのだから。-P401
『ヒロインズ』の最終頁をなんども読んでは、心をふるわす。わたしもヒロイン。小説というジャンルにとらわれなくていい。ブログをつづけたいし、育児のことも、もっと書きたい。いつか自分でzineもつくりたい。
「あなたは何からはじめる?」
わたしたちは、いつだって何だってはじめられる。
初出:『ヒロインズ』の読書体験をシェアするzine 『私たちの午前三時』(C.I.P.BOOKS)/ 2019年1月発行
こちらのzineはただいま、東京・学芸大学の書店「SUNNY BOY BOOKS」で販売中のようです。オンラインストアにて在庫がありました◎
その後の、親愛なるヒロインズ

いまは冬。ぎゅうと、胃を掴まれるような痛みで目覚め、ほんとうにお酒には弱くなったなぁと、昨夜あったことを反芻する朝。となりで眠っている娘の目がうすく開いたかと思うと、わたしの掛け布団のなかへ、いきおいよく滑りこんでくる。
−昨年末のことだろう、ブログの日記が、書きかけのまま止まっている。娘はもうすぐ三歳半で、夜泣きはしなくなってから、ずいぶん経った。あいかわらず夜は、娘といっしょにすぐ眠ってしまう。たまに起きていても、物事をふかく考える力は残っていなくて、冷んやりした台所の床に座りこみ、iPhoneの画面をぼーっと見ている。布団のなかで、文章を書くことは、もうずっとしていない。
頻繁にではないが、夜ひとりであそびに出かけることも、増えてきた。最終のバスで帰宅して、先に娘が寝息をたてている、布団のなかに潜りこむと、そこはとてもあたたかい。
先日もわたしは出かけていた。名古屋・東山にある書店「ON READING」で始まった、植本一子さんの写真集『うれしい生活』(河出書房新社)の出版を記念した展示(2/24まで開催中)と、トークイベントに参加するためだ。
(自分の日記を本(zine)にすることにおいて、植本さんの『かなわない』(タバブックス)をはじめとする(その前の『働けECD』もすきだったけれど)、著作に影響を受けていないことなんて、あるのだろうか……とまずは思わずにはいられない。だがいま、ここでは割愛する)
植本さんがイベント内で仰っていたことが、約一年前、ケイト・ザンブレノ『ヒロインズ』(西山敦子訳、C.I.P.BOOKS)の感想などを集めたzine(以下、感想zine)に、自分が寄稿した文章を書いてから、思っていたこととかさなり、はっとした。
それは、フェミニズムについて、勉強していないと、発言をしてはいけないような気がしてしまう、ということだった。
植本さんは、勉強をしようと本を手にとるが、腹立たしくなって、なかなか読みとおせないとも、仰っていた。「どう思う?」とパートナーに問いたくなって(例にだされていたのが夫婦別姓のこと)、微妙な空気になってしまうらしい。
『ヒロインズ』を読了したあと、わたしもフェミニズムやジェンダーに関する本を何冊も、手にとった。それでも、ぜんぜん読めていなくて(読めたのはイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ』すんみ、小山内園子訳、タバブックス くらい……)、植本さんの話には、大きくうなずくばかりだった。
もちろん、勉強しないと発言してはいけない、なんてことはないと、植本さんは言っていて、わたしも同じことを、自分の寄稿文を読みかえしたときに感じていた。そのことだけはわかる。そんなことはないんだ、ということは。
とくに、自分の場合は「読まなければいけない」と思ってしまう本は、どんなジャンルであれ、読まなくなってしまうのだ。それは『ヒロインズ』を読む前に、名作だから読まなければと積んでいた、フィツジェラルドを読めなかったことと、そんなに変わらないのではないか(ギャツビー、読んだら面白かった)。
勉強しなくていいと思っているわけではない。でも、まだまだ自分にかけている、圧みたいなものから解放されたい。そして、もっと自分の身近に引きよせて、フェミニズムについて考えたい。このことにたいして、わたしは途中でもなく、まだ入り口にいるだけかもしれない。ゴールのないことのようにも、思える。
日記zineが完成してから、『ヒロインズ』のことをずっと考えつづけていた。自分が変わったと思えたのも、ひとや本との出会いがあったからだ。感想zineに参加したことがきっかけで、zineをつくる方とも交流できた。元々ファンだった、きくちゆみこさんの言葉とも、出会いなおせたような気持ちになった。わたしにとって、彼女のつくるzineはお守りのようで、その言葉の一つひとつが、「つくりたい」という火を、いつも心に灯してくれる。
そういえば、ゆみこさんの自己紹介zine『こんにちは。あなた わたしはきくちゆみこです』を、さいきん手にいれたばかりだ。自分もかつて、自己紹介zineをつくりたいと思っていたことを、思い出す。感想zineの発行後、版元のある、静岡県・三島で開かれた読書会に、参加する際に持っていきたかったのだった。自分も含めた家族の体調不良で、参加は叶わず、zineはラフの状態だ。
それでいいと、いまは思う。ゆみこさんのzineを読みながら、自分の願いは、だれかが叶えてくれているのだ、というような気持ちになってくる(なんだか自分から出てきた言葉ではなくて、SNSで見かけた発言のような気もするが)。それはまだ、うまく言葉にできない気持ちだ。例えば、自分がこの先つくりたいと思っている内容の本を、だれかがいまつくっている最中だったりすることがある。それでも、時間のなさを嘆いたり、焦るような気持ちが前よりなくなった。
すこしずつしか進めない。でも、夫と組んで本をつくることが(それも楽しく!)できるなんて、一年前の自分は思っていただろうか。
むしょうに、『ヒロインズ』を読んでいた頃を振りかえりたくなって、感想zineに寄稿した文章を、そのまま転載した。そのことを、こころよく承諾してくださった、版元の主宰であり翻訳者でもある西山敦子さんが、先日東京の二子玉川で開催された「本屋博」で、わたしたちのzineを買ってくださっていたことを知り、胸がいっぱいになった。本当にありがとうございました。
ばんかおり